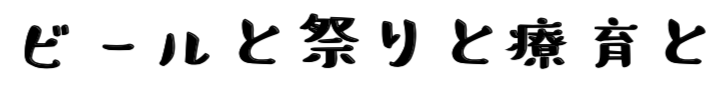一番最初に目の当たりにした一番険しい山をついに越えた!〜自閉症子育てマンガ「かにママのABA療育日記」008
 「かにママABA療育日記」第8作です。
「かにママABA療育日記」第8作です。


 7年前、「つみきの会」に入ってABA(応用行動分析)による家庭療育を始めたばかりの頃のエピソードで、過去2回書いてきたマンガの続きです。
7年前、「つみきの会」に入ってABA(応用行動分析)による家庭療育を始めたばかりの頃のエピソードで、過去2回書いてきたマンガの続きです。
イスに再び座ることができるようになるだけで、これだけハードな試練があったのです。
この、一番最初に目の当たりにした一番険しい山を越えることができなければ、家庭療育を現在まで続けることはできなかったでしょう。
最初の数日間は、泣き続ける息子に妻が「根負け」して、抱っこし、外に連れ出してもらえました。
これにより当時の息子は、泣き続けることで「イヤなこと(=イスに座る)」を回避でき、「好きなこと(=ママに抱っこしてもらえる+外にお出掛けする)」が手に入ると学びました。
泣き続けるという行為が「強化」されてしまうわけです。
間違った「強化」を繰り返せば繰り返すほど、あとで修正するのが大変になります。
マンガに書いた当時の「誤った強化」は数日間でしたので、「50分間泣き叫ぶのに耐える」ことで消えましたが、「泣けば親は自分の言うことを聞いてくれる」という誤った強化を半年、1年、5年、10年と繰り返していたら…。
修正するのに年単位の時間がかかったかもしれませんし、「ママを殴れば言うことを聞いてくれる」といった具合にエスカレートしていたかもしれません。恐ろしいことです。
息子が2歳半の段階で「勝利」したことにより、妻は現在に至る約7年間、ほぼ毎日、家庭療育を続けることができました。
そして息子は今も、腕力が強くて体も声も大きい男のぼくより、家庭療育を続けてきた妻の言うことを聞きます。
家庭療育に直接関わっていないぼくは、息子に「なめられている」感じもします。
それでいいのです。
にほんブログ村
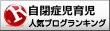
自閉症児育児ランキング