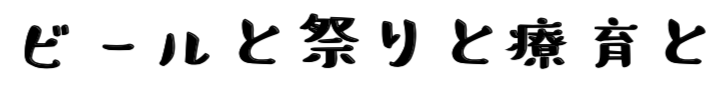療育手帳Aの重度自閉症・知的障害児だって、「スモールステップ」で根気強く教えていけば、いろんなことができるようになる〜自閉症子育てマンガ「かにママのABA療育日記」011
 「かにママABA療育日記」第11作です。
「かにママABA療育日記」第11作です。

 今回は、「スモールステップ」についてです。
今回は、「スモールステップ」についてです。
健常児ならいつの間にか自然にできるようになることの多くが、自閉症児にはなぜかできません。
妻とぼくもそうでしたが、親が健常者でかつ障害に関する知識がないと、「この子はなぜこんな簡単なことができないのだろう」と不思議に思い、「こんな簡単なことをどうやって教えたらいいのだろうか」と途方に暮れ、「こんな簡単なことができないわが子は将来どうなってしまうのだろうか」と絶望してしまいます。
でも、「教えたいこと」を細かい単位に分解して、その細かいことを一つずつ、根気よく教えていけば、できるようになるのです。
自閉症・知的障害といっても「障害の重さ・軽さ」「できること・できないこと」は人それぞれでしょうが、少なくとも、自閉症も知的障害も重度であるとお墨付きをもらったわが息子は、このスモールステップの手法で、多くのことができるようになりました。
妻は「つみきの会」のテキスト「つみきブック」に沿ってABA(応用行動分析)を使った家庭療育を進めてきましたが、その時々の必要に迫られて、テキストに載っていないことを自己流で教えてきています。
その第一弾が8年前、息子が2歳半ぐらいの頃に教えた「帽子をかぶる」でした。
熱射病の心配があるので外出時に帽子をかぶらせるのですが、最初は怒るわ泣き叫ぶわでまったくかぶってくれませんでした。
でも、妻が何カ月もかけて根気強く教えていくと、かぶることができるようになりました。「障害があっても、教え方次第でなんとかなるんだ」ということを知ることができたのは大きかったです。
トイレでの排せつもスモールステップで何年もかけてマスターしました。服のボタンをかけること、ヒモを結ぶこと、アナログ時計を読むこと、今や彼の一番の楽しみである自転車もそうです。
お子さんの「できることが増える」と、そのお子さん自身のためになことはもちろん、子育てがラクになります。
親がラクをするためにも、ABAの家庭療育は有効なのです。
にほんブログ村
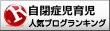
自閉症児育児ランキング